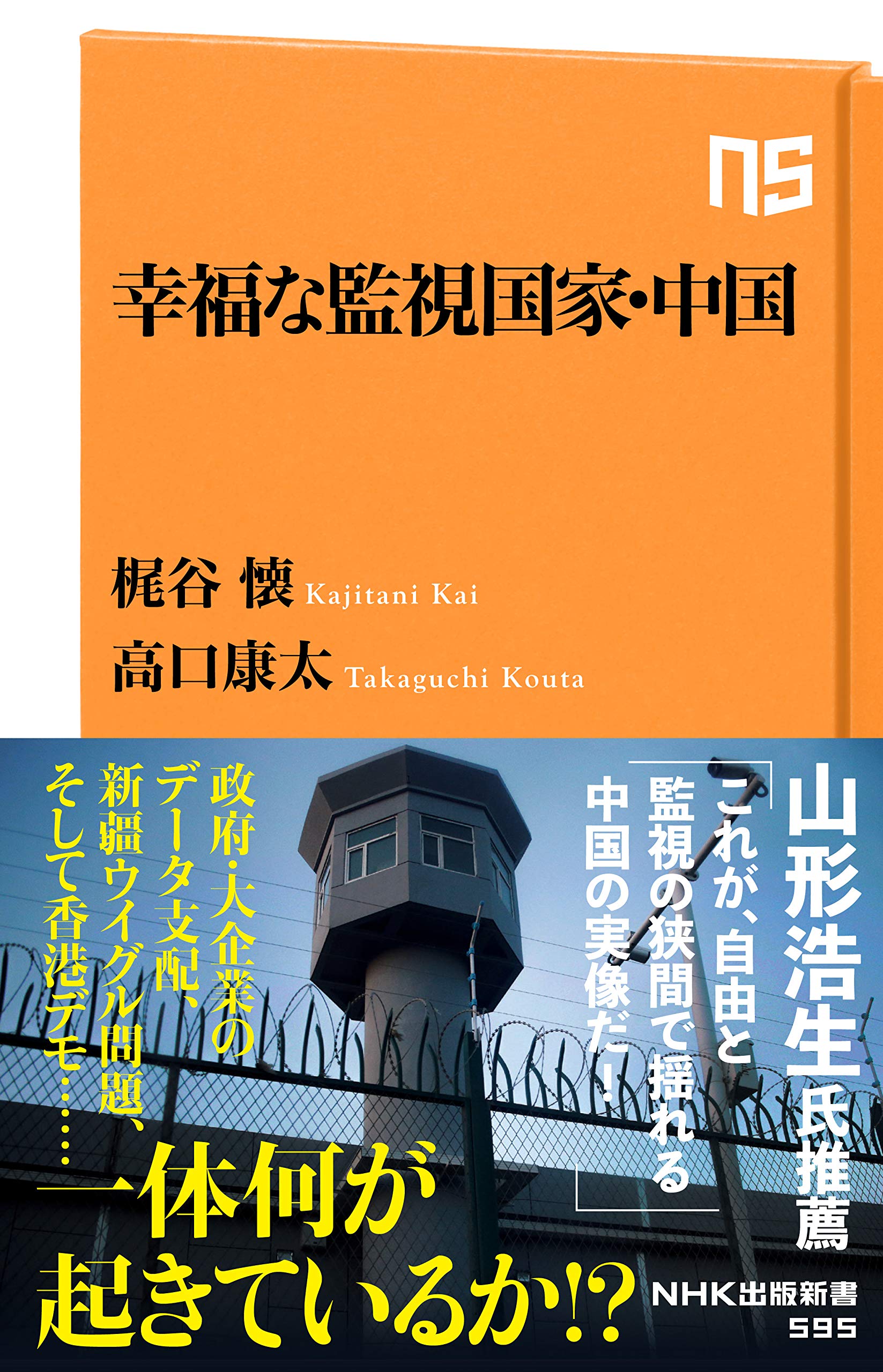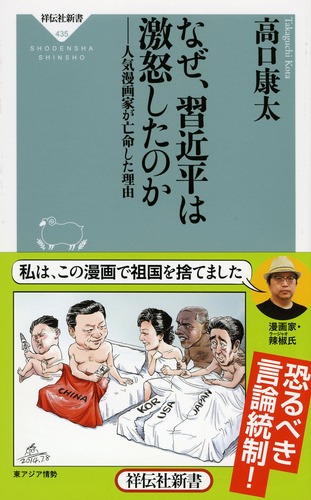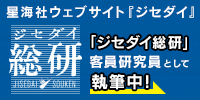中国、新興国の「今」をお伝えする海外ニュース&コラム。
- 中国-社会
- 中国-政治
- 中国-経済
- 中国-文化
- インド
- ロシア
- ブラジル
- 東南アジア
- アフリカ
- 欧州
- 南北アメリカ
- オセアニア
- 香港・台湾
- 韓国・北朝鮮
- 三面記事
- ネット
- ガジェット
- スポーツ
- エンタメ
- 書評
- 写真
- 動画
- コラム
- 注目ニュース
- 月別人気記事トップ10
新車初回購入者に対する税還付策=洪水も重なり悲惨な結果に―タイ(ucci-h)
2011年12月18日
■新政権下、車の初回購入者に税額割引が行なわれて2ヵ月半......■
*当記事は2011年12月16日付ブログ「チェンマイUpdate」の許可を得て転載したものです。
といった議論はやめておきましょう。
車にかかる物品税(小型乗用車だと30%と大きい)を10万ドル(約779万円)まで、初回購入者に限り(若年層が多くなろう)、乗用車は1500ccクラスまで、来年2012年末までに限って実施、あとから税還付してやろうという政策である。

THAILAND dealer for test driving use. / woody1778a
■続々と噴出しだしたデメリット
メリットの少なさに比べて、デメリットが続々と噴出してきた。
しかしまあ、連立政権の公約である。輸入車や中古車、1600ccも含めよとの要望もあったが、そのまま9月16日から実施した。しかし、その後に洪水がやってきた。車を買うどころではなくなった人も多い。また自動車、部品工場も水に浸かってしまった。
■洪水も重なり、予想を上回る効果薄......
というわけで、想像通り、幸か不幸か、今年の出足はきわめて低かった。物品税局によると、9月16日から11月末日までの2ヵ月半で、1380件の申請しかなかったという。うち一番メリットがある乗用車が1024件と、4分の3を占めた。還付額にして1億800万バーツ(2億6800万円)。1台平均7万8000バーツ(約19万4000円)だ。
財務省は、最初の1年で50万台の購入者が申請するだろうと見込んでいたが(予算300億バーツ(約746億円)。1台平均6万バーツ(約14万9000円))、足元にも及ばない実績となりそうだ。
■水が引けば増える?とも思えない
今後、洪水が引け、自動車会社の供給も増えてくれば申請件数は上がってくるだろうが、予定通りにはいきそうもない。
おそらく、車代が安くなった代わりに背伸びして購入する若年層が増える。そうなると、推測だがローンの借り入れ条件が厳しくなっているのではないだろうか。5年間転売できないという縛りもあり、途中手放すわけにも行かず、二の足を踏む者も出てくるだろう。
住宅の新規購入優遇と同じで、「公約は果たしました。結果は、結果に聞いてください」ということになるのだろうか。

*マティチョンの報道。
関連記事:
【タイ大洪水】都は沈むのか?政府発表も混乱=インラック首相の目に涙(ウチャ)
【タイ大洪水】工場再開は来年5月!?明暗を分けたトヨタとホンダ(ucci-h)
家が買えない!都市民の悲哀と悪辣業者を描いた社会派ドラマ「蝸居」を見た―中国農業コラム
住宅バブルの化けの皮=虚偽銀行ローン問題が明るみに
米IBMが発表、「世界自動車通勤苦痛指数」=中国の渋滞は限界に
中国高官がトヨタ社長を痛烈批判=プラグイン・ハイブリッド技術をめぐる駆け引き(明天)
【写真】公費乱用を隠す奇策?!ベンツをホンダ車に改造したニセパトカー登場―広西チワン族自治区
*当記事は2011年12月16日付ブログ「チェンマイUpdate」の許可を得て転載したものです。
*当記事は2011年12月16日付ブログ「チェンマイUpdate」の許可を得て転載したものです。

SANY0021 / Thant Zin Myint
インラック・タイ貢献党連立内閣が2011年7月に成立してから5 ヶ月がたったが、当初のポピュリスト的政策の良し悪しの論議は、10月以降のタイの歴史的大洪水で押し流されてしまった。ここまで、インラック政権は、「洪水対策内閣」の趣で来た。
洪水の水もようやく引いてきたので、再びタイ貢献党の政策、米価の引き上げ、最低賃金の引き上げ、学卒新入社員の15000バーツ(約3万7800円)の月給、自動車・住宅の初回購入者への減税、ガソリン価格の引き下げ等、形だけのものも含めて、いろいろあるが、これらの政策の状況を徐々に追ってみよう。
■自動車初回購入者への物品税還付策
Bangkok / *** Harold R ***
まずは、自動車の初回購入者への物品税還付の政策だ。時間が経ったので、中身を確認しておこう。高価な新車を買いたいが、高いので手が届かないという可哀想な人たちに対し、車にかかる物品税分を引いて買いやすくしてやろうというのが、この政策の趣旨である。
車と住宅の初回購入者に大きな財政支援(チェンマイUpdate、2011年8月24日)
「こんなに車が売れている時世に、さらに道路に車を増やす必要があるの?」
「なぜ、もう少しで手が届きそうな人だけを助ける必要があるの?」
といった議論はやめておきましょう。
車にかかる物品税(小型乗用車だと30%と大きい)を10万ドル(約779万円)まで、初回購入者に限り(若年層が多くなろう)、乗用車は1500ccクラスまで、来年2012年末までに限って実施、あとから税還付してやろうという政策である。

THAILAND dealer for test driving use. / woody1778a
■続々と噴出しだしたデメリット
メリットの少なさに比べて、デメリットが続々と噴出してきた。
・「国産車だけを優遇するとは、国際貿易ルール違反の保護主義だ」と、車輸出国のマレーシアやインド、中国からクレームがきた。
・メーカーも「せっかくエコ・カーの開発に努めてきたのに、物品税が17%と低いから、メリットが低くて不利になる」と喜んでばかりもいない。
・車を初めて買うのは、多くは若い連中だ。「ローンが途中で払えなくなる問題が出る」「原油輸入が増える。道路に排気ガスまき散らされ、若い連中の交通事故が増える」と反対する声が出てきた。
しかしまあ、連立政権の公約である。輸入車や中古車、1600ccも含めよとの要望もあったが、そのまま9月16日から実施した。しかし、その後に洪水がやってきた。車を買うどころではなくなった人も多い。また自動車、部品工場も水に浸かってしまった。
■洪水も重なり、予想を上回る効果薄......
というわけで、想像通り、幸か不幸か、今年の出足はきわめて低かった。物品税局によると、9月16日から11月末日までの2ヵ月半で、1380件の申請しかなかったという。うち一番メリットがある乗用車が1024件と、4分の3を占めた。還付額にして1億800万バーツ(2億6800万円)。1台平均7万8000バーツ(約19万4000円)だ。
財務省は、最初の1年で50万台の購入者が申請するだろうと見込んでいたが(予算300億バーツ(約746億円)。1台平均6万バーツ(約14万9000円))、足元にも及ばない実績となりそうだ。

*bangkok postの報道。
■水が引けば増える?とも思えない
今後、洪水が引け、自動車会社の供給も増えてくれば申請件数は上がってくるだろうが、予定通りにはいきそうもない。
おそらく、車代が安くなった代わりに背伸びして購入する若年層が増える。そうなると、推測だがローンの借り入れ条件が厳しくなっているのではないだろうか。5年間転売できないという縛りもあり、途中手放すわけにも行かず、二の足を踏む者も出てくるだろう。
住宅の新規購入優遇と同じで、「公約は果たしました。結果は、結果に聞いてください」ということになるのだろうか。

*マティチョンの報道。
関連記事:
【タイ大洪水】都は沈むのか?政府発表も混乱=インラック首相の目に涙(ウチャ)
【タイ大洪水】工場再開は来年5月!?明暗を分けたトヨタとホンダ(ucci-h)
家が買えない!都市民の悲哀と悪辣業者を描いた社会派ドラマ「蝸居」を見た―中国農業コラム
住宅バブルの化けの皮=虚偽銀行ローン問題が明るみに
米IBMが発表、「世界自動車通勤苦痛指数」=中国の渋滞は限界に
中国高官がトヨタ社長を痛烈批判=プラグイン・ハイブリッド技術をめぐる駆け引き(明天)
【写真】公費乱用を隠す奇策?!ベンツをホンダ車に改造したニセパトカー登場―広西チワン族自治区
*当記事は2011年12月16日付ブログ「チェンマイUpdate」の許可を得て転載したものです。